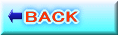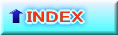| 「臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律」改正案国会を通過,1年以内に施行へ! | |
| これまでの経緯 | |
昭和33年衛生検査技師法,昭和46年臨床検査技師法がそれぞれ施行され,半世紀の歳月が流れた。この間,日臨技としては多くの会員の要望と熱意を受け,理事会内に法改正推進対策委員会を設置,国民の公衆衛生並びに医療に貢献すべく,真の臨床検査を目指し法律改正に向け鋭意努力を行ってきた。
しかしながら,旧態依然として厚生労働省では,新しい法律改正を好まず一部の生理検査の業務拡大をみるにとどまった。その後,この機を大きく動かしたのは「日本臨床検査技師連盟」の存在であった。平成10年当時,連盟発足の是非をめぐり会員の意見が大きく割れた経緯もあった。
しかし,議員立法によって制定された臨衛技法は「議員の力」を借りずして改正することはできずとの観点から,日臨技のコントロールの下,明けて平成11年1月発会式を迎えた。これにより厚生労働省では,議員を通じて法改正に着手せざるを得なくなったのである。
防衛に回った厚生労働省では平成14年10月,省内に「臨床検査技師,衛生検査技師に関する在り方等検討会」を発足させ,5回にわたる会合を開くなか,日本医師会,日本臨床検査医学会をはじめ業務制限はもとより,医師の指導監督すら除くことはできないとした意見をまとめた(平成15年5月)。この経緯は業務制限の難しさを多くの会員及び関係者に知らしめることとなったのである(日臨技HP渉外活動参照)。
| 国会提出へ向けて | |
検体検査の中で微生物,輸血,細胞判定に関わる検査項目だけでも制限を設け突破口を開こうと個別に日本医師会に繰り返し申し入れるも,「検査研究発展の妨げになる」「現に職務に就いているものが失職する」「規制緩和の時代にそぐわない」「無資格者による事故事例がない」など時期尚早であるとの理由で物別れに終わった。
一方,「日本臨床検査技師連盟」では,与党3党(当時は保守党が存在)を中心に都道府県技師会の協力を得ながら地元議員との関係を取りつつ着実に網の目を広げ,平成15年2月12日公明党内(24議員)に,3月5日自由民主党内(96議員)に相次いで議員連盟を発足していただき,国会上程へ向けての拍車が掛かった。
これより議員連盟加入国会議員と良好な関係を保つ一方,改めて日本医師会,厚生労働省への陳情に明け暮れたが進展をみることはなかった。進まぬ交渉に「通る法案も通らなくなる」との危機感から,平成16年3月に入り自民,公明両党の中で党内手続きを進め,堀内光雄総務会長(当時),安部晋三幹事長(当時)など総勢30名の法案に賛成する議員の連名にて,3月23日「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に提出する運びとなった。
しかしながら,この法案に会員の悲願であった業務制限の一文字も入ることはなかった。
| 提出から1年 | |
議案が上程されると後は審議待ちとなる。流れは衆議院厚生労働委員会→衆議院本会議→参議院厚生労働委員会→参議院本会議→成立となる。途中での一休みは廃案となるので,審議が始まれば一気に成立まで持ち込まなければならない。他に提出されている重要法案と国会会期との睨みあいが続く中,第159通常国会,第160臨時国会,第161臨時国会と会員共々に気を揉みながら行く末を見守った。
この間,最も影響力のある日本医師会の了解を得るために再度交渉に入った。折しも,日本医師会ではその執行体制が変わったことが大きく影響し,業務制限に関する文言を罰則規定がない努力規定として加えることを了承。厚生労働省もこれに賛成し,法案の一部訂正に力を注いでくれた。この法案はもめて長引くと廃案となる可能性も心配される中,「委員長一括提案」による審議なしで衆議院を通過させる準備に取りかかった。
これにより熊代昭彦(自民岡山二区)・江田康行(公明九州比例)両議員と共に厚生労働部会長,厚生労働委員長,厚生労働委員会理事,与野党厚生労働委員各位に対して法案の趣旨説明を行い,提案内容を了解していただくという段取りを行った。
| 突然の朗報 | |
各議員へ行脚を続ける中,朗報が飛び込んできた。その結果,平成17年3月25日衆議院厚生労働委員会(鴨下一郎厚生労働委員長)を通過,翌週29日衆議院本会議を通過,即日参議院に送られたのである。
参議院では先に述べた附帯決議に関わる質疑応答があるとされていたとおり,平成17年4月21日に開催された参議院厚生労働委員会(委員長:岸宏一参議院議員,自民山形選挙区)では,民主党・足立信也参議院議員(大分選挙区),日本共産党・小池晃参議院議員(比例),社会民主党・福島瑞穂参議院議員(比例)らの約1時間10分に及ぶ質疑応答があり,尾辻秀久厚生労働大臣(自民九州比例),鴨下一郎衆議院厚生労働委員長(自民東京比例),岩尾總一郎厚生労働省医政局長がこれに答弁し,その結果,全会一致で承認され,参議院本会議に送られて翌4月22日可決成立した.